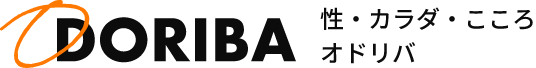生理用品の費用に負担を感じたり、買いたいのに買えず困ったりすることはありませんか?
そのような場合、「生理の貧困」に陥っているかもしれません。
この記事では、生理の貧困について、日本の現状や相談先などを解説します。
生理の貧困とは
「生理の貧困」とは、経済的な理由で生理用品を十分に購入できなかったり、生理についての理解不足によって支援を受けられなかったりする状況を指します。
この言葉が広く知られるようになったのは、2021年のコロナ禍がきっかけです。経済的に不安定な状況が続く中、生理用品を十分に購入できない女性がいるという実態が注目を集め、「生理の貧困」という言葉が社会に浸透しました。
ただし、経済的な事情により生理用品を入手できない状況は、コロナ禍以前から存在していた問題です。今では、女性の健康や人権の課題として、社会全体で考えるべきテーマとなっています。
生理の貧困がもたらす影響

生理の貧困は、決して特別な人だけの珍しい問題ではありません。
健康、日常生活、さらには社会や経済にも影響を及ぼす、私たちにとって身近な問題です。ここでは、生理の貧困によってどのような影響が生じるのか、3つの側面から見ていきましょう。
健康への影響
十分な生理用品を購入できないと、以下のような健康上の問題が起こることがあります。
厚生労働省の調査によると、生理用品の不足によって「かぶれ」「かゆみ」を経験したと答えた人は、それぞれ全体の73.5%、71.5%にのぼりました。(「よくある」「ときどきある」の合計)
また、「外陰部のかゆみ」「おりものの量や色の異常」「外陰部の赤みやにおいの変化」も半数以上が経験しており、それぞれ55.7%、53.0%、51.0%となっています。
一つひとつの問題は軽く見られがちですが、放置すると腹膜炎や不妊症などの重い病気につながる可能性もあります。
生活への影響
生理の貧困は、以下のような生活や精神面に影響を及ぼすことがあります。
こうした状態が続くと、学校や仕事を休みがちになったり、人との交流を避けるようになったりするなど、日常生活に支障をきたす可能性もあります。
社会・経済的な影響
生理に関する理解不足は、個人の問題にとどまらず、社会や経済にも影響を及ぼします。
たとえば生理に対する理解が十分でない職場では、「生理休暇を取りたい」と相談しづらく、体調がつらくても無理をして働かざるを得ない状況になることがあります。
こうした我慢や不安が重なれば、集中力の低下やパフォーマンスへの影響にもつながります。
生理にともなうさまざまな症状により、日本国内で年間4911億円の労働損失が生じていると推計されています。生理の貧困は個人の問題だけでなく、社会全体へも影響を与える課題といえます。
日本で生理の貧困が起こる原因

生理の貧困は、単にお金がないという問題に止まりません。
経済的な事情に加え、社会的な価値観や家庭環境など、複数の要因が重なって生じるケースもあります。日本における生理の貧困の主な原因を、3つの側面から見ていきましょう。
経済的な問題
「生活が厳しく、十分な生理用品を購入できない」といった経済的な問題は、生理の貧困を引き起こす大きな理由です。
令和4年に厚生労働省が実施した調査によると、新型コロナウイルス発生後、生理用品の購入・入手に苦労したことが「よくある」「ときどきある」と回答した女性は全体の8.1%にものぼりました。その多くが、30歳未満で年収300万円未満の層に集中しています。
とくにコロナ禍は、ひとり親世帯の生活に大きな打撃を与えたと知られています。
また、限られた収入やお小遣いの中で、食費や通信費、学費などが優先され、生理用品の優先度が低いという調査結果もあります。
生理用品は、毎月必要な生活必需品です。たとえば、12歳から50歳まで生理があると仮定し、1ヵ月あたり1,500円かかるとすると、生涯で約70万円の支出になります。
このように、生理にかかる費用は決して小さくなく、経済的な負担が積み重なることで、節約の対象とされてしまうこともあるのです。
社会的な意識と偏見
生理に対する社会の価値観や偏見も、生理の貧困を深刻化させる原因の1つです。
たとえば、生理用品を購入する際に紙袋や黒いビニール袋に包む店舗があります。これは「生理は恥ずかしいもの」「隠すべきもの」という意識が今も残っているあらわれと考えられます。
生理に関する悩みは人に打ち明けにくく、自分の状態が普通なのか分からずに不安を抱える人も少なくありません。
「生理用品が買えないなんて意味不明」「生理痛で休むのは甘え」などの発言は、こうした社会的な空気のなかで生まれています。
こうした誤解や偏見が、生理の貧困をさらに見えにくくし、問題がより深刻化しているのです。
家庭環境の影響
家庭内で生理に関する知識が不足していたり、生理への関心が薄かったりすると、子どもが十分な生理用品を得られない状況が生じることがあります。
たとえば、シングルファーザーの家庭や適切な養育がおこなわれていない環境では、そのような状況が起こりやすいとされています。こうした場合、子どもは限られたお小遣いで生理用品を買わなければならず、十分に用意できないこともあるでしょう。
また、親に相談しづらい家庭環境では、生理に関する悩みをひとりで抱え込み、生理の貧困につながりやすくなります。
生理の貧困を解決するための取り組み
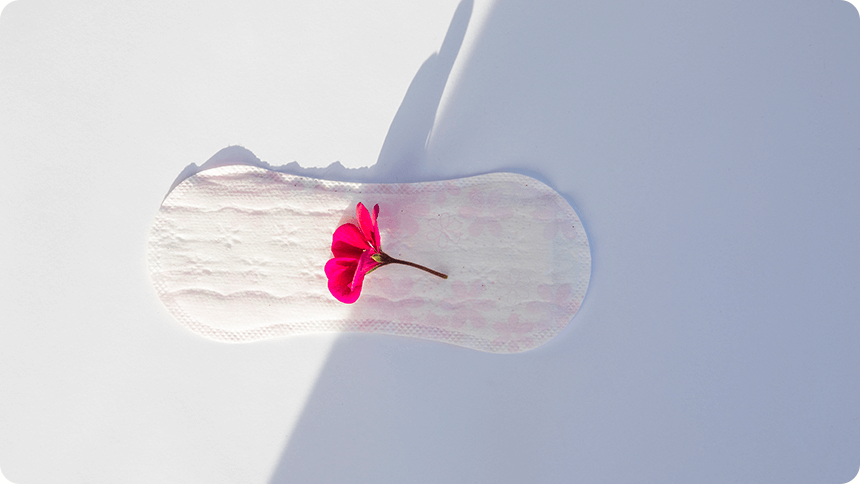
生理の貧困は、恥ずかしいことではありません。
世界的にも生理の貧困は問題視されており、日本でも国や地方自治体、学校などで女性の健康をサポートするための取り組みが実施されています。
自治体の支援
令和6年の調査では、全国926の地方公共団体が生理の貧困に関して取り組みを実施していることが明らかになっています。予算で購入したり寄付を受けたりした生理用品の無料配布を行っているケースが、多く見られます。
1回分の無料配布ではなく、ナプキン1パックや昼用・夜用を組み合わせたセットなど、生理用品の不足を補える量を提供している自治体も珍しくありません。
配布方法は自治体ごとに異なり、役所の窓口での提供、公共施設のトイレに設置などさまざまです。支援を受けたい場合は、お住まいのある自治体のホームページなどで確認してみましょう。
学校のサポート
学生の場合、学校のサポートを利用するのもひとつの選択肢です。
各学校にある保健室では、突然の生理や生理用品を十分に用意できないなどの学生に対して、生理用品を提供しています。学校のトイレに生理用品を備えている場合もあるため、必要なときは活用するとよいでしょう。
また、養護教諭は生理に関する相談も受け付けています。親に生理の知識が乏しく理解が得られない、生理について話しにくい家庭環境であるなどの場合は、保健室で相談することも可能です。
「こんなこと相談していいのかな」とひとりで悩まず、困ったときには気軽に頼ってみましょう。
支援団体によるサポート
女性を支援する団体、NPO、地域の女性支援施設が実施する生理用品の寄付や無料配布を受ける方法もあります。
また、自治体によっては、フードバンクと提携してひとり親を支援する取り組みもおこなっています。
支援が必要なときは、団体のホームページなどを活用して情報を探してみましょう。
海外における生理の貧困への取り組み
海外でも生理の貧困は深刻な社会課題として注目されており、各国でさまざまな取り組みが実施されています。
取り組みの一部を、以下に紹介します。
必要とするすべての人が無償で生理用品を入手できる法律が成立した(2022年8月)
【ニュージーランド】
小学校・中学校にて無料で生理用品を配布
【フランス】
再利用可能な生理用品の購入費用の一部または全部を医療保険が負担する
(対象:26歳未満または低所得の女性)
【カナダ・インド・オーストラリア】
生理用品は課税対象外とする
また、生理の貧困は「誰ひとり取り残さない」という理念のもとに進められているSDGs(持続可能な開発目標)にも深く関わる課題です。
生理の貧困は一人ひとりの問題ではなく、社会全体で向き合い、解決に向けて取り組むべき重要なテーマといえるでしょう。
生理の貧困は身近な問題!困ったら相談しよう

生理の貧困は、経済的事情や社会的な意識・偏見、家庭環境などの理由が重なって起こる身近な問題です。放置すると健康や生活へ影響するだけでなく、社会全体の損失にもつながります。
近年では世界的にも注目されており、日本でも厚生労働省が調査を実施したり、相談窓口や支援体制の整備が進められたりしています。
学校や公共施設のトイレに備えられた生理用品を利用する、無料配布を受ける、生活に関する悩みを相談する。そうした行動は、生理の貧困を乗り越えるきっかけになります。
生理の貧困は決して恥ずかしいことではなく、自分だけで抱え込む必要はありません。
困っていることがあれば、自治体や学校の保健室などの窓口へ気軽に相談してみてくださいね。