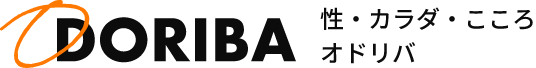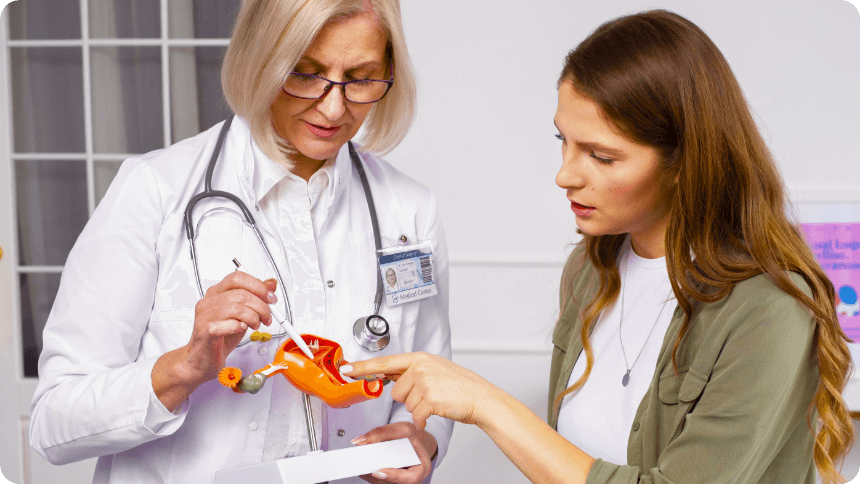生理痛や生理不順、その他、女性特有の困りごとを相談したいけれど、産婦人科に行くのは怖い…とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。とくに内診は産婦人科特有の診察ですから、未経験の方にとっては怖いと思ってしまうのも自然なことですよね。
この記事では、産婦人科を受診する前に知っておきたい診察の流れや心構え、診察をスムーズに受けるためのポイントを紹介します。
産婦人科で相談できる症状は?
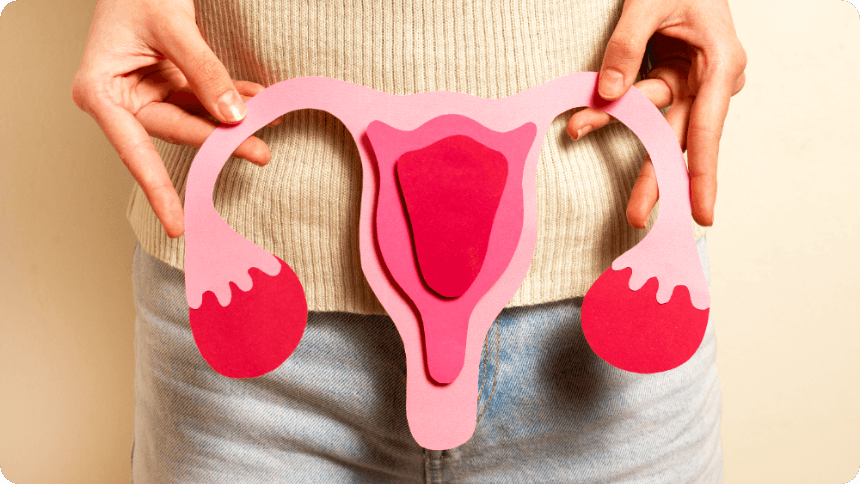
産婦人科は、子宮や卵巣、外陰部など女性特有の臓器や体の部位を扱う診療科です(乳房は乳腺外科が担当)。
対象年齢は幅広く、気になる症状や悩みがあれば年齢に関係なく受診することができます。未成年の場合には、基本的に保護者の同伴が求められますが、中学生・高校生・大学生など学生さんも、もちろん受診が可能です。相談できる主な症状を、以下にまとめました!
月経にまつわる悩みやトラブル
生理痛や生理不順、月経の量が多い、PMSに悩んでいる方は、ぜひ一度相談してみましょう。月経にまつわる不調がある場合には、保険診療で低容量ピルの処方や、子宮内に女性ホルモンを放出する器具を装着する選択肢が提案される場合があります。
この器具は避妊だけでなく、月経困難症や月経過多の症状を軽減する効果が期待できます。ただし、適用されるかどうかは、医師が症状や状態を詳しく診断した上で判断します。
このほか、旅行や受験など大切な日に合わせて月経を調整したい場合も相談可能です。直前の受診では対応できないことも多いため、早めの受診がおすすめです。
妊娠・分娩に関連すること
妊娠の有無を確認する段階から、その後の妊婦健診、分娩に至るまで、妊娠にまつわる一連の相談ができます。不妊の相談には、不妊治療を専門にしたクリニックや、生殖医療に特化した医師が在籍するクリニックを選ぶと良いでしょう。
反対に、望まない妊娠を避けるための相談も可能です。避妊の失敗などは、身近な人には相談しにくいもの。困ったときこそ、産婦人科に頼ってみましょう。
子宮や卵巣を中心とした、骨盤の中にある臓器のトラブル
子宮がんや卵巣がんといった悪性腫瘍、子宮筋腫やポリープなどの良性腫瘍、子宮内膜症など、子宮や卵巣に起こるトラブルは、産婦人科の守備範囲です。このほか、性器脱、尿失禁もカバーしてくれます。
なお、悪性腫瘍は発見が遅れると命に関わることもあります。定期的な婦人科検診や、子宮頸がんワクチンの接種についても相談してみましょう。
加齢に伴う女性特有の症状
更年期障害に伴うホットフラッシュ(のぼせ・ほてり・発汗など)や、イライラ感・不眠・倦怠感・肩こり・頭痛などの相談ができます。
いざ産婦人科へ!診察までの流れを解説します!
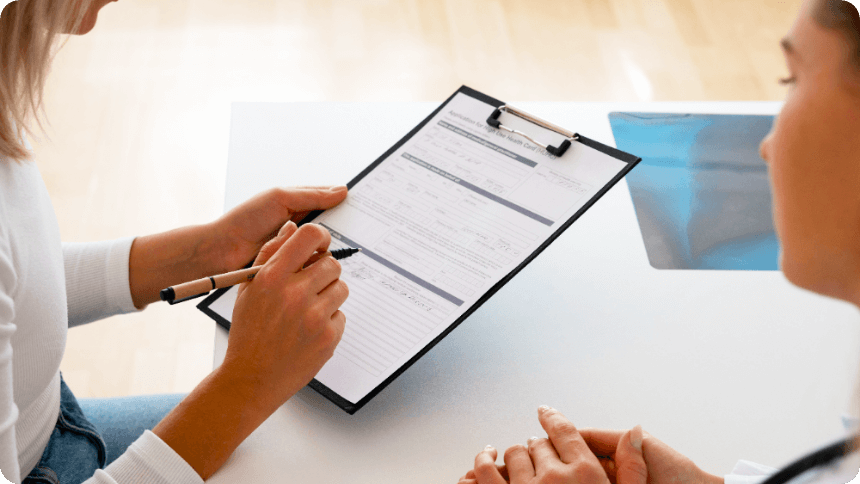
初めて産婦人科を受診する場合、大学病院のような大きな病院ではなく、まずは身近なクリニックに行ってみましょう。特に最近は完全予約制のクリニックも増えているので、事前にホームページで予約方法や診療内容をチェックするのがおすすめです。
受診の当日、クリニックで受付をすませたら、診察の前に「問診票」を記入します。問診票には、相談したい症状だけでなく、日頃の月経について(いつ始まったか、最終月経はいつか、周期、持続期間、出血量、月経痛の有無)、性交渉の経験、妊娠・分娩の経験などを記入します。
人には話しにくい内容もあるかもしれませんが、いずれも診断・治療をする上で必要な情報です。可能な限り正確に記入しましょう。あらかじめ生理周期や医師に伝えたいことは、メモをしておくとスムーズです。
中学生・高校生など、未成年の女性が受診する場合は、保護者の同伴が望ましいとされています。性交渉の有無など、問診に答えにくいケースを考慮し、保護者に席を外してもらうこともできますが、止むを得ない事情の場合は、単独で受診することも可能です。ただし、家族への説明が必要と医師が判断した場合、次回の診察は保護者の同席を求められることがあります。
いよいよ診察!内診が怖い…痛い?拒否できる?

初めての内診は不安や緊張を感じる方も多いかもしれません。しかし、内診は医師が正確な診断を行うために重要な手技で、患者の同意を得た上で行われます。
ここでは、内診の目的やプロセス、痛みについて解説します。
内診とは
内診とは、医師が腟の中に指や腟鏡、経腟超音波などの器具を入れて子宮、卵巣、腟の状態を把握する診察方法です。患者さんの状態を把握する上で非常に重要な手技のひとつで、実施する際には、患者さんに必要性を説明し、同意を得てから行われます。内診は医師と患者さんの二人きりで行われることはなく、女性看護師や助産師が立ち会います。
内診をする際は、内診台と呼ばれる椅子のような診察台に座ります。この台は自動で動き、上向きで脚を開いた体勢をキープしてくれます。患者さんの状態にあわせて、負担がかからないように内診台の高さや角度を調節することもあります。はじめての方にとっては少し抵抗感を覚える体勢かもしれませんが、医療従事者と患者さんの間にカーテンをつけるなど、患者さんの恥ずかしい気持ちや不安感を軽減するための工夫が施されています。
内診の目的は?
内診の目的は、おもに以下の3点です。
・下腹部の痛みがあるか、またその痛みの箇所を確認する
・子宮や卵巣に筋腫や腫れなどの異常がないか調べるる
・子宮の大きさや位置、周辺の組織と癒着していないかなどを確認する
内診の際に「腟鏡」という器具を使うこともあります。これは性器出血の有無やその発生部位の特定、おりものの状態や子宮頸部の異常を調べるときなど、診察や検査に活用されます。
内診は拒否できる
内診には必ず患者さんの同意が必要です。どうしても気が進まない場合は、拒否することもできます。とくに、性行為の経験がない患者さんの場合には、痛みや恐怖心等への配慮から、内診を実施しないケースもあります。
内診ができない場合は、経腹エコー(お腹の上からのエコー検査)や経直腸エコー(お尻の穴からのエコー検査)で骨盤内の異常を確認します。また、一般の診察ベッドに横になった状態で、外陰部の視診を行うこともあります。異常が疑われる場合、MRI 検査を検討することもあります。
内診は痛い?
内診の痛みの感じ方には個人差があります。SNSでは「声が出るほど痛い」「激痛!」といった投稿が目立ち、不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、深呼吸をして、できるだけ力を抜くことで、内診による痛みが緩和できると言われています。
また、医師も手指や器具を温めたり、潤滑ゼリーを使用したり、痛みを軽減する工夫をし、患者さんができるだけ快適に内診を受けられるよう配慮しています。
スムーズな診察のためのポイント
診察を受ける時の服装は?
内診をする場合は下着を脱ぐ必要があるため、丈が長めで裾が広がるゆったりとしたフレアスカートがおすすめです。下着を脱ぐだけでサッと準備ができるので、検査までの流れが非常にスムーズです。内診台で医師の診察を待っている間も、スカートが下半身を覆ってくれるので、心理的なストレスも少なく済むでしょう。
生理中の受診は避けたほうがいい?
産婦人科に関連する悩みや症状がある場合は、月経周期に関わらず受診して構いません。月経痛などの相談であれば、基本的には月経周期に関わらず診察できます。
ただし、子宮頸がん検査など、月経開始直後を避けた方がよい検査や、月経の終わりに近い時期に発見しやすくなる疾患もありますが、これらは医師が診察してみないとわからないことも多いため、受診の段階で気にする必要はありません。なお、出血している場合は、診察する時にシートを敷くなどの対応をしてくれます。
持ち物は?
マイナ保険証や、支払いに必要な現金・クレジットカードなど、通常のクリニック受診でも必要なもののほか、産婦人科特有の持ち物として、内診後に出血した場合を想定し、おりものシートを準備しておくと安心です。クリニックで用意されている場合もあります。
内診には同意が必須。怖がらず、女性特有の悩みは産婦人科へ!

産婦人科は中学生、高校生から閉経後の方まで、幅広い年齢層の女性の健康をサポートする診療科です。初めての受診では内診が怖い、痛いのでは?という不安を抱くこともあるでしょう。
しかし、内診は必須ではなく、必要と判断され実施する場合でも、患者さんの同意を得て行われます。医療機関側も、できるだけ痛みを軽減し、患者さんの負担を減らせるよう工夫をしています。
月経や妊娠などの悩みがある方は、心配しすぎず、一度気軽に受診をしてみてはいかがでしょうか?早めの相談が、ご自身の健康を守る第一歩です。