キスやオーラルセックスは「挿入がないから安全」と思われがちですが、実はいくつかの性病(性感染症)はこれらの行為で感染する可能性があります。自分やパートナーの健康を守るためにも、リスクを正しく理解することが大切です。この記事では、キスやオーラルセックスによって感染する可能性のある性病や予防策について詳しく解説します。
なお、医学的には「性感染症」という名称が一般的ですが、この記事では「性病」という表現で統一しています。
性病(性感染症)とは?

まずは、性病とはどのような病気か、基本的な知識を確認しましょう。
性病の定義とリスク
性病は、性行為によって感染する病気の総称です。ウイルスや細菌、寄生虫などの病原体が、血液や精液、腟分泌液を介して、粘膜や皮膚の傷から体内に侵入することで発症します。
多くの性病は初期症状が軽い、または無症状で気づきにくく、知らないうちに感染を広げてしまうことも少なくありません。放置すると不妊症や重篤な合併症、命に関わるケースもあるため、正しい知識と早期発見・治療が大切です。
性病は性器のみにうつるわけではない
性病は性器同士の接触だけでなく、口と性器の接触(オーラルセックス)や肛門への挿入(アナルセックス)でも感染する可能性があります。ウイルスや細菌などの病原体は、血液や体液を通じて粘膜に入り込むため、口やのど、肛門でも感染するリスクがあります。
キスで性病はうつる?
「キスで性病に感染するの?」と不安に思う方もいるでしょう。結論としては、可能性はゼロではありませんが、リスクは極めて低いとされています。
ただし、口の周りに症状が出る性病として、口唇ヘルペスや梅毒などが挙げられます。これらは唾液や口内の潰瘍(かいよう:体の中の皮膚や粘膜がただれて、深く傷ついた状態のこと)から病原体が侵入する可能性があり、口腔内に傷や口内炎がある場合は感染リスクがわずかに上昇します。
なかでも口唇ヘルペスは、母子感染や日常のキスなどでもうつることがある一方、口に症状がある状態でオーラルセックスを行うと、性器ヘルペスとして感染が広がるケースがあるため、性感染症としても扱われています。
軽いフレンチキス程度であれば感染リスクはほとんど無視できるレベルですが、口腔内に傷や口内炎があるときはキスを控えるなど、思いやりのある行動が大切です。
オーラルセックスでうつる性病とは?
オーラルセックスは、性器と口が直接接触するため、性病の感染リスクが高くなります。キスに比べ、感染する病気の種類も多くなるのが特徴です。
口や咽頭にうつる性病はどんな病気?

キスやオーラルセックスで感染する可能性のある代表的な病気について、それぞれ症状や治療法を解説します。
ヘルペス
口や性器に水ぶくれや潰瘍を作る、ウイルス性の病気です。
初めて感染した場合は症状が重篤で、発熱や倦怠感、強い痛みを伴います。女性の場合、口の中に症状が出ると水分が取れなくなったり、性器に症状が出現すると排尿や歩行も難しくなるほど痛み、入院するケースもあります。
一度感染するとウイルスは神経に潜伏し、体調不良やストレス、生理をきっかけとして再発することがあります。抗ウイルス薬で症状を抑えますが、潜伏しているウイルスを完全に除去することはできないため、根治は困難です。
梅毒
梅毒の初期症状として、感染した部位に痛みのないしこりが現れますが、無症状のことも少なくありません。
皮膚や粘膜で感染した梅毒の原因菌は血流にのり、全身に広がります。進行すると、全身に発疹やリンパ節の腫れ、胃潰瘍、肝炎、腎炎など様々な臓器の障害が現れる場合があります。
無治療のまま数年から数十年経過すると、心臓や血管、神経などの重要な臓器に合併症を起こし、命に関わります。治療は、抗生物質の服用や注射です。
近年梅毒が急増しており、2015年までの報告数は1年あたり1000件に満たなかったものの、2022年以降は毎年1万件を超えています。
クラミジア
性器や咽頭、目に感染する性病で、日本で最も多く、特に若い女性に多いという報告があります。
性器に感染した場合、おりものの増加やかゆみ、不正出血などの症状が出ることがありますが、女性の半数以上は無症状です。放置すると、骨盤腹膜炎や子宮付属器炎を起こし、不妊症のリスクが高まります。
咽頭に感染した場合、のどの腫れや痛みが出ることもありますが、多くは無症状とされています。
性器に感染がある女性のうち、、10~20%は無症状であっても咽頭のクラミジアも陽性になると言われています。
治療は抗生物質の内服です。性器よりも咽頭の方が治療に時間がかかるという報告があります。
淋菌
性器、咽頭、直腸、目などに感染し、クラミジアに似た症状を引き起こす性病です。
無症状のことも多く、放置すると不妊症やHIV感染リスクが高まります。咽頭に感染しても無症状の場合が多いものの、性器に感染した際にのどを検査すると10~30%が陽性になると報告されています。
治療は抗生物質の内服が基本ですが、最近耐性菌の増加も報告されており、一度の治療で完治しないことがあります。そのため、治療後には効果判定のための検査が必要です。
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)
エイズの原因となるウイルスで、性交渉、母子感染、血液感染などにより広がります。
感染後2~4週間で、のどの痛みや発熱、倦怠感などインフルエンザに似た症状が出現しますが、自然によくなり、潜伏期間に入ります。数年~十数年経過すると徐々に免疫力が低下し、命に関わる感染症やがんを発症します。
唾液や涙に含まれるウイルスは、含まれていたとしてもごくわずかです。また、体の外に出るとすぐに感染力を失う非常に弱いウイルスであり、日常生活での感染リスクは極めて低いと言われています。
抗ウイルス薬の開発が進み、適切な時期に発見・治療できればエイズへの進行を抑えられますが、根治はできません。
HPV(ヒトパピローマウイルス)
性器やのど、肛門、皮膚に感染するウイルスです。性器に感染した場合、鶏のトサカのようなイボができる「尖圭(せんけい)コンジローマ」や、子宮頸がんを引き起こすことが知られています。
のどに感染すると、中咽頭がんの原因となります。HPV感染のみでは特徴的な症状はありませんが、中咽頭がんに進行するとのどの痛み、違和感、飲みこみにくさなどの症状が出現します。
HPV感染そのものに対する治療法はありませんが、ワクチン接種により予防が可能です
感染を防ぐためにできる4つのこと

オーラルセックスを含め、感染を防ぐ方法について解説します。
1. コンドームを使用する
性病の多くは、性器同士の接触や体液を介して感染します。そのため、コンドームを正しく使用することが最も基本的な予防策です。
適切に使用することで感染リスクを大きく減らすことができるため、たとえオーラルセックスのみでもコンドームを使用するようにしましょう。
2. 定期的に性病検査を受ける
何らかの症状があるときはもちろん、パートナーが変わった時や不特定多数と性交渉を持った時、またはそのような相手と性交渉を持った時は検査を受けましょう。
「症状がない=感染していない」とは限りません。特に性器に感染がある場合は、咽頭も調べましょう。
3. 口腔内の健康を保つ(傷・口内炎の有無)
口内炎や傷、できものがあるときはキスやオーラルセックスは避けましょう。粘膜に傷があると、ウイルスや細菌が体内に侵入しやすくなり、性病に感染するリスクが高まります。小さな傷でも油断せず、口腔内の健康状態を確認することが大切です。
4. HPVワクチンの接種を検討する
HPVワクチンは性器だけでなく、咽頭への感染も防ぐと言われています。
現在、小学校6年~高校1年生女子を対象に定期接種が推奨されています。対象年齢の方や接種を希望する方は、早めに検討しましょう。
もし性病にかかってしまったら?
万が一、自分が性病に感染したとわかったら、以下の対応をとりましょう。
パートナーにも検査を勧める
せっかく自分が治療を受けても、相手が未治療だと再び感染する「ピンポン感染」の恐れがあります。感染が分かったら、パートナーにも検査と治療を促すことが重要です。お互いの健康を守るためにも、しっかり話し合いましょう。
治療が完了するまでは、性交渉しない
治療後も一定期間の経過観察や、完治したかどうかの確認が必要です。
治療の途中で薬をやめたり、耐性菌が原因だったりすると、菌が体内に残って完全に治りきらない場合があります。その状態で性交渉をもつと、相手に感染させてしまうリスクがあるため、医師の許可があるまで性行為はもたないようにしましょう。
キスやオーラルセックスでも性病はうつるリスクあり!
性病は、性器だけでなく口やのどにも感染する可能性があります。軽いキスでの感染リスクは低いものの、オーラルセックスでは粘膜の接触があるため感染リスクが高まります。
性病は、放置しても自然に治ることはありません。少しでも気になる症状があれば、皮膚科、耳鼻科、婦人科などの医療機関を受診し、早めに対処しましょう。正しい知識と行動で、自分と大切な人を守ることができます。
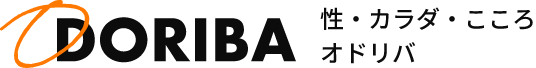







 https://odoriba.love/sex/2472/
https://odoriba.love/sex/2472/









