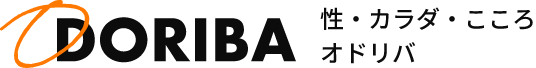寒い季節の到来とともに感じる体の冷え。夏は冷房が効きすぎているせいで、1年中体の冷えが気になっている方もいるのではないでしょうか。
世間では「子宮を温めるとよい」と言われることがありますが、それは本当に科学的な根拠があるのでしょうか。
今回は、子宮を温める効果について、科学的な視点を交えながら正しい知識をお伝えします。さらに、温活がもたらすメリットや具体的な方法についても解説するので、冷えが気になる方はぜひ参考にしてください。
「子宮を温めるとよい」と言われる背景
世間的に「子宮を温めるとよい」とされる理由について紐解いていきましょう。
東洋医学において「冷え」はさまざまな不調の原因と考えられています。冷えによる血行の悪化と、月経不順や生理痛などの症状が関連づけられているのです。
近年、健康維持や美容のために、日常的に体を温める「温活」が広がりを見せています。冷えと不快な症状に関連があるならば、温めることでその症状を抑えたいと考えるのは、自然なことです。
温活は、妊活や生理痛の緩和など、健康維持を意識した生活を送りたいというニーズの高まりが背景にあると考えられます。
子宮を温める効果はあるの?
世間では「お腹を温めるといいよ」とよく言われていますが、過度に気にする必要はないでしょう。
現在のところ、子宮を温めると妊娠しやすくなるという研究結果はありません。間接的ではありますが、高温が妊娠に良い影響をもたらさない可能性も考えられています。
一例を挙げると、妊娠初期に高温環境にいた女性の流産率が高まることが報告されています。
「体の中までじっくり温めたい」そんな思いから、サウナで極限まで暑さに耐えたり、高温のものを長時間直接お腹に当てたりするのは控えた方が良いでしょう。
腹巻きなどを使い、穏やかに温める方法は選択肢の1つです。
子宮だけが問題?冷え性とは

冷えがあると、子宮まで冷えているのでしょうか?冷え性とはどういうものなのか、医学的な観点から解説します。
冷え性では体のどこまで冷えている?
医学的に「冷え性」という疾患名はありませんが、他の人が寒さを感じない環境でも、寒さや冷えを感じるものと定義されています。
冷え性は病気ではないものの、冷えに付随する症状に多くの女性が悩まされており、冷え性を自覚している女性は男性の2.8倍にのぼるとの報告があります。
冷え性の方の多くが、手先・足先の冷えを訴えており、深部体温の指標となる鼓膜の温度と、指先の温度差が6℃以上あることが分かっています。
手先、足先の冷えを感じる冷え性では、末端の体温だけでなく、全身の体温が下がっているように感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、冷え性の方でも、全身の体温は正常値を示している場合がほとんどです。
もし治療が必要なほどの低体温であれば、体は激しく震え、意識がもうろうとするなどの症状が現れるでしょう。
以上を考慮すると、冷え性であっても、子宮を含めた内臓までもが冷えているとは考えにくいのです。
冷え性の原因とは
基礎疾患がない場合、冷え性は自律神経機能の調整不良による末端の血流量の低下が原因と考えられています。
自律神経は、自分の意志とは関係なく、臓器に対して働きかけます。寝ているときでも呼吸をしたり心臓が動き、寒暖差があるところでも体温を一定に保つなど、意識していなくても生きていけるように常に働いています。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、交感神経は体を緊張させ、副交感神経はリラックスさせます。
自律神経の乱れにより交感神経の緊張が高まると、手先や足先の血管が収縮し、血流量が低下します。これが、冷えにつながるしくみです。
冷え性の方は、冷え性でない方に比べ、安静時の交感神経活動が高く、副交感神経活動が低いことが明らかになっています。自律神経の働きを乱し、交感神経の活動を高める要因として、次のようなことが挙げられます。
- 女性ホルモンバランスの崩れ
- ストレス
- 過度なダイエット
- 生活習慣の乱れ
- 基礎代謝量の低下
世間の温活ブームとの向き合い方
温活が広がる背景には「冷えが不調を招く」という、東洋医学の中でも冷えだけに着目された考えや、SNSでの情報共有があります。
一方で、科学的なエビデンスは十分ではなく、個々の実感を中心に温活が広がっているのが現状です。
温活を取り入れほっと一息つく時間をとることは、ストレス緩和に役立ちます。
しかし、行き過ぎた温活は体にとってストレスとなることもあります。
温活は、体に無理のない範囲で取り入れるのが良いでしょう。
温活を無理なく日常生活に取り入れるには?
日常生活に取り入れやすい温活方法をご紹介します。
体を温める食材を選ぶ
東洋医学では、食物を体を温める「陽性食品」と体を冷やす「陰性食品」に分ける考え方があります。
カテゴリー別に、それぞれの例を見ていきましょう。
・炭水化物もち米
小麦、大麦、はと麦
牛肉、鶏肉、羊肉
ベーコン、豆腐
玉ねぎ、ピーマン、かぼちゃ、小松菜、かぶ、ねぎ
セロリ、竹の子、なす、トマト、きゅうり、レンコン
桃、さくらんぼ、みかん、ゆず
いちご、すいか、メロン、バナナ
味噌、酢、酒、ごま油、黒砂糖
しょう油、塩、白砂糖
紅茶
ウーロン茶
上記は陽性食品と陰性食品の一例です。ただし、体を温めたいからといって、陰性食品を完全に避ける必要はありません。
食事を摂る上で最も大切なのは、バランスの良い食事を心がけることです。たとえば、白砂糖を黒砂糖に変えるなど、無理のない範囲で取り入れやすいものから試してみてください。
リラックスタイムを取り入れる
ストレスは、交感神経活動を活発にさせる要因です。交感神経活動が活発になると末梢の血管が収縮し、末梢の血行不良が起こりやすくなります。
意識的にリラックスタイムを取り入れて、副交感神経活動を優位にする時間を取りましょう。
アロマオイルを使って香りを楽しんだり、好きな音楽を聞いたりしながら、体も心も休まる時間を過ごすと、自然と緊張もほぐれることでしょう。
運動で基礎代謝量アップを目指す
筋肉量を増やす運動をして、体が生み出せる熱量を増やしましょう。体温調節のための熱を生み出すのは、骨格筋と呼ばれる筋肉です。筋力アップのために、筋トレを週2~3回のペースで行いましょう。
冷え性の女性は、冷え性でない女性に比べ、基礎代謝量や筋肉量が低いということが分かっています。男性より女性に冷え性が多いのも、男女の基礎代謝量や筋肉量の違いによるものだと考えられています。
トレーニングの負荷は無理なく段階的に増やし、コツコツと習慣化することがポイントです。
生活習慣を改めよう
冷えが気になる方は、今一度、ご自身の生活習慣を見直してみましょう。
心がけたいポイントは、以下の通りです。
- バランスの取れた食事
- 十分な睡眠
- 適度な運動
- 禁煙
タバコに含まれるニコチンには血管を収縮させる作用があるため、喫煙は末梢の血流を悪くする原因になります。
また、栄養バランスの崩れた食事や睡眠不足、過度なダイエット、運動不足による筋力低下は、基礎代謝を落とす原因となります。
生活習慣は、いわば生活の土台です。自律神経機能を整え、はつらつとした毎日を送るためにも、生活習慣を整える意識を持つことが大切です。
子宮を温める効果を正しく知り、健康的なライフスタイルを実現しよう

子宮を温める効果について、科学的根拠は乏しいものの、冷えの改善・不妊対策・生理痛の緩和などを目的に温活を取り入れる人が増えています。
これは、健康意識の高まりから、自分の体に向き合い、より良い状態を保ちたいという思いの表れともいえるでしょう。
温活を実践する際は、食事や運動などの生活習慣を整え、ストレスケアなどバランスよく取り入れることが大切です。
体を温めることで得られるリラックス効果や健康への意識を高め、毎日を快適に過ごしていきましょう。