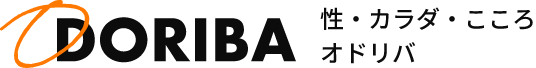多くの女性に共通する体臭の悩みには、汗だけでなく、加齢やホルモン、ストレスなど、色々なものが影響します。
本記事では、体臭をいい匂いにするために、体の内外からケアする方法をご紹介します。周りに「いい匂い」と思ってもらえるように、ぜひ試してみてください。
体臭の悩みは誰にでもある
体臭の悩みは、多くの女性に共通する問題です。実際に、30代〜40代の女性1,101人を対象にした調査では、以下のような結果が報告されています。
- 約8割が体臭に悩みを抱えている。
- 約6割が自分で体臭に気づいている。
- 日中の汗や洗濯物、枕などの寝具の臭いから自分の臭いに気がついた人が多かった。
- 約7割が体臭ケアとして何らかの対策を実践している。
- 約8割が周囲の不快な臭いが気になった経験がある。
- 特に香水や汗、ワキの臭いが気になった。
出典元:株式会社オールアバウト ロート製薬株式会社|<女性の体臭に関する調査>
こうした結果から、多くの女性が体臭の悩みを抱えながらも、何らかの対策に取り組んでいることがわかります。
体臭が発生する原因は?

体臭が発生する原因には、皮膚表面の成分による反応、加齢やホルモンバランスの変化、ストレスなどが関与しています。
なぜ体臭の原因になるのか、詳しくみていきましょう。
汗・皮脂・雑菌の影響
体臭の原因は汗そのものではなく、汗による皮膚環境の変化にあります。汗が皮膚表面の皮脂や垢、タンパク質などと混ざり、これを皮膚の常在菌が分解・酸化すると、におい成分が発生します。
また、汗には「エクリン腺」と「アポクリン腺」という二種類の汗腺から出るものがあります。エクリン腺からの汗は全身から分泌され、成分のほとんどが水分のため無臭です。
一方、アポクリン腺からの汗は、ワキや陰部など限られた部位から出てきます。アポクリン腺から出る汗にはタンパク質や脂質が多く含まれ、エクリン腺の汗とは成分が異なるのです。そのため、アポクリン腺からの汗は、体臭に関わるにおいのもとになります。
このように、体臭の強さは汗の種類や皮脂の分泌量、皮膚の常在菌の種類といった皮膚環境によって左右され、個人差が大きく現れます。
加齢や女性ホルモンの影響
加齢や女性ホルモンの変化は、体臭に大きく関係しています。
一般的に想像される加齢臭は、皮脂中に含まれる不飽和脂肪酸が分解されて生じる「2-ノネナール」という物質が原因とされます。皮脂の分泌は男性ホルモンによって促進されるため、一般的に男性に臭いが強く現れる傾向がありますが、女性でも無関係ではありません。
更年期以降は女性ホルモンの減少によって皮脂分泌が増え、加齢臭が強くなる傾向がみられます。また、年齢に伴って皮脂の分泌量や組成に変化が生じると、2-ノネナールの生成が促進されることも明らかになっています。
さらに、近年の研究では、女性ホルモンバランスの周期的な変化によっても体臭の成分が変化することがわかってきました。特に排卵期には、フェロモンのような効果を持つ体臭が増加することも示されています。
ストレスの影響
近年、ストレスや睡眠不足が皮膚から独特の臭いを発生させやすくなることが明らかになっています。心理的なストレスや蓄積した疲労、睡眠不足が皮脂や皮膚の状態に影響を与え、皮膚から特有のにおい成分を放出しやすくするためです。
体臭をいい匂いにする方法5選

ここで、日常的に取り入れやすい体臭ケアの方法をご紹介します。体の外側からのアプローチはもちろん、目に見えない体の内側からのケアも欠かせません。
できることから、無理なく試してみてください。
1. 皮膚の清潔を保つ
体臭をいい匂いにするためには、皮膚を清潔に保つことが重要です。皮膚に付着した汗や皮脂、老廃物を洗い流すことで、体臭の原因となる細菌の増殖を予防できます。
毎日の入浴やシャワーで汗や汚れを落としましょう。特に運動後や汗をかきやすい夏場はこまめに服を着替え、早めに汗や皮膚表面の汚れを洗い流すことが効果的です。
ただし、洗いすぎると皮膚の乾燥や善玉菌の減少につながり、かえって体臭を悪化させることがあります。善玉菌は皮膚のバリア機能や潤いを保つ役割があるため、ゴシゴシ洗いすぎないよう注意しましょう。
2. 洗濯法や服の素材に気を付ける
不快な体臭を防ぐためには、衣類の洗濯習慣と素材選びも重要です。衣類の臭いは主に汗や皮脂、細菌によって発生しますが、繊維の素材によって臭いの残りやすさが異なります。
特に、ポリエステルなどの合成繊維は細菌が繁殖し、臭いが残りやすい傾向があります。一方で、綿やウールなどの天然繊維は吸湿性や抗菌性に優れており、悪臭を抑える効果を持っています。
汗をかいた後の衣類はこまめに洗う、消臭効果のある洗剤を使う、などの洗濯法の使い分けも効果的です。
3. 食べ物を見直す
体臭をやわらげたいときは、食べ物の見直しも効果的です。食事内容によって汗の匂いの質が変わることが、いくつかの研究で報告されています。
たとえば、脂質や肉、卵、大豆製品を多く摂る人は、比較的不快ではない体臭の汗をかきやすいのに対し、炭水化物を多く摂りすぎると、不快な体臭につながる汗をかきやすい傾向が示されました。
また、食事のカロリー制限を行った人は一時的に体臭が強くなったものの、制限を解除すると体臭が改善されたと報告されています。
さらに、果物や野菜を多く摂ることで肌のカロテノイド量が増え、花や果実のような汗の匂いと関連することも研究で示されています。
4. ストレスを軽減する
ストレスの軽減も、「いい匂い」の体になるためには欠かせません。ストレスや感情の変化、心理的な緊張が汗や皮脂の分泌を変化させ、不快な体臭を強めてしまうためです。
リラックスして良好な生活リズムを保つと、汗の成分や分泌量が安定して心地良い体臭に近づきます。一方で、睡眠不足や過度のストレスで分泌物が変化し、体臭がきつくなることが報告されています。
ストレスコントロールは、自信を持って過ごせるような「いい匂い」づくりにも役立つでしょう。
5. フレグランスなどを適度に利用する
フレグランス製品の適度な利用は、体臭を好ましい印象に整え、自信を持って過ごすために効果的です。
実際に、香りをまとっていると自然な体臭よりも好ましく感じられ、魅力的な印象を残すことが示されています。
気に入ったデオドラントや香水を使うことで、体臭の印象をコントロールし、周囲に良い印象を与えられるでしょう。ただし、香りの好みには個人差があります。使い過ぎてかえって不快に感じられないよう、注意が必要です。
いい匂いになると起こる、プラスの影響

自分にとっても他人にとっても、お気に入りの香りや匂いはメンタルによい影響を与えます。他人に「いい匂い」と思われると、人間関係もスムーズになるでしょう。
前向きな気分になれる
人は、好きな香りに包まれていると、気持ちが前向きになりやすくなります。
香りは「心地よさ」や「安心感」などの肯定的な感情を引き出す一方で、嫌いな香りは敵意などの否定的な感情を生むこともあります。
実際に、約40%の人が自分の好みの香りを日常的に使い、90%近くの人が香りによって癒しや疲労回復を感じている、という報告がありました。また、アロマセラピー経験者の多くが「心地よかった」「落ち着いた」と感じており、香りがポジティブな感情に関わっていることがわかります。
「いい匂い」と感じる好きな香りを取り入れることは、気分の調整や自分らしさの表現に重要な役割を持ち、前向きな気持ちを生み出すのに役立つでしょう。
人間関係がスムーズになる
体臭が「いい匂い」と感じられると、人間関係がスムーズになることが示されています。人がパートナーの体臭に慣れて親しみを感じると、絆や満足感が深まるためです。
恋人の体臭に自然と親しみを感じるようになって関係が良くなり、関係が悪くなると体臭を嫌いになる傾向も報告されています。
また、「香水などのフレグランスを含めた匂いが心地よいと感じると、初対面の人でも友達になりやすい」という研究結果も示されています。
体臭を「いい匂い」と思ってもらえると、恋愛や友人関係において相手との距離を縮めるきっかけとなるでしょう。
「いい匂い」を身にまとって、毎日を楽しく過ごそう
体臭の悩みは誰にでも起こりうるもので、加齢やホルモンバランスの変化など、自分ではコントロールしにくい原因もあります。
それでも、体の外側と内側から丁寧にケアを続けることで、少しずつ「いい匂い」に近づくことができます。肌や衣類を清潔に保つ、フレグランスを活用する、健康的な食事やストレス管理をするなど、毎日の小さな積み重ねが自分自身への自信と周囲との心地よさにつながっていきます。
毎日を楽しく過ごせるように、無理をせず自分のペースで取り組めることから始めてみましょう。