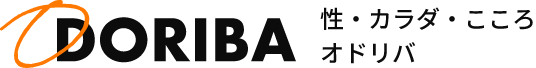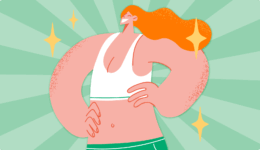更年期を迎えると、女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、ほてり、発汗、気分の落ち込みなど、心身のさまざまな変化が現れやすくなります。また、この時期には骨密度の低下による骨粗しょう症や、糖尿病などの生活習慣病のリスクも高まることが知られています。
ホルモン補充療法(hormone replacement therapy:HRT)は、減少した女性ホルモンを補い、症状を和らげる治療法です。一方で、副作用や注意点もあり、「自分に合っているのか」「どれくらい続けられるのか」と不安に感じる方も少なくありません。
この記事では、ホルモン補充療法(HRT)の仕組みからメリット・リスク、治療を受ける際の流れまで、わかりやすく解説します。
閉経前にも更年期症状は起きる
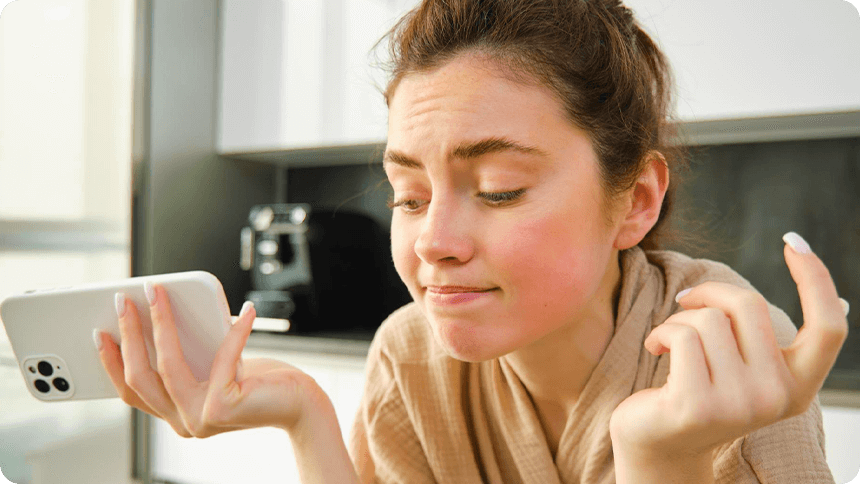
閉経とは、卵巣の働きが停止し、12か月以上月経が来ない状態を指します。その前後の約10年間が「更年期」と呼ばれ、この時期はホルモンの変動により、心身にさまざまな影響が現れやすくなります。
更年期症状とは、閉経をはさむ時期に現れる多様な不調で、他の病気が原因ではないものを指します。ほてり・のぼせ・疲労感・めまい・動悸・肩こり・不眠・イライラなどが典型的で、閉経前でもこうした症状が出ることがあります。
ホルモン補充療法(HRT)とは
更年期障害の主な原因は、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少することです。ホルモン補充療法(HRT)は、これを補充することで症状を改善する治療法です。
ここでは、具体的なホルモンの種類や投与方法をみていきましょう。
使用するホルモンの種類
治療に用いられるのは、エストロゲンとプロゲステロンの2種類のホルモンです。
更年期症状の改善には、本来エストロゲンだけで効果がありますが、単独で使用すると子宮体がんのリスクが高まる可能性があります。そのため、子宮がある場合はプロゲステロンを併用するのが原則です。
一方で、子宮を摘出している場合はプロゲステロンの使用は不要となります。
投与方法
ホルモンの投与方法には、内服、貼付剤(テープ)、塗布薬(ジェル)などの種類があります。
内服薬
・コレステロールや中性脂肪の改善に効果がある
デメリット
・乳房不快感、乳房痛がある
・肝障害が出ることがある
外用薬(テープ、ジェル)
・血栓症のリスクが低い
・肝臓への負担が少ない
デメリット
・皮膚がかぶれることがある
・薬の種類によっては、内服と外用薬の併用が必要になるため、飲み忘れに注意が必要となる
投与法の種類
ホルモン補充療法には、ホルモンをどのようなスケジュールで投与するかという「投与法」にも種類があります。
薬の種類や投与方法は、ライフスタイルや体質に合うものを選ぶことが大切です。
周期的投与法
21〜25日の周期でエストロゲンとプロゲステロンを投与し、定期的に出血を起こす方法。閉経前で定期的な出血に抵抗がなければ選択されやすい。
持続的併用法
エストロゲンとプロゲステロンを連続投与し、出血を起こさない方法。閉経前に始めると不正出血が出る場合がある。
閉経前にホルモン補充療法(HRT)を始めるメリット

閉経前から更年期障害の治療を始めることに抵抗を感じる方も少なくありません。
しかし、閉経前からホルモン補充療法を開始することで、更年期障害のつらい症状を早期に和らげ、生活の質を維持しやすくなるでしょう。
具体的には、次のようなメリットが期待できます。
- 【更年期症状の改善】ホットフラッシュ、不眠、関節痛などの不快な症状を改善させます。
- 【気分の安定や認知機能低下の抑制】抑うつ状態の改善、認知機能低下に効果があるとされています。
- 【骨粗しょう症の予防】骨密度が増加し、将来の骨折のリスクを低下させます。
- 【腟や尿道の萎縮症状の改善】腟の乾燥や性交痛、頻尿などを改善させます。
- 【生活習慣病のリスク低下】脂質代謝・糖代謝の改善や血管保護作用により、生活習慣病のリスクを下げる効果が期待できます。
- 【悪性腫瘍のリスク低下の可能性】大腸がん、胃がん、食道がん、肺がんのリスク低下の可能性があります。
- 【その他】白内障の発症予防、歯周疾患などの発症予防や歯を失うリスクを減らします。
ホルモン補充療法(HRT)の副作用・デメリット
HRTには多くのメリットがありますが、副作用やデメリットも存在します。治療を始める前に、あらかじめ知っておくことが大切です。
- 【副作用の出現】乳房の張り、不正出血、頭痛などのマイナートラブルが起きることがあります。
- 【長期使用によるリスク】血栓症、脳卒中(高血圧の方)、動脈硬化(糖代謝異常がある方)、子宮体がん、卵巣がん、乳がんのリスクが上昇する可能性があります。
ホルモン補充療法(HRT)のリスクを下げるには?
ホルモン補充療法のリスクは、適切な工夫によって軽減することが可能です。体質や持病によって最適な方法は異なるため、必ず医師と相談しながら治療を進めましょう。
具体的に、以下のような方法がリスクの軽減に役立つとされています。
- 【エストロゲンの投与量を変える】必要最小限の量にし、副作用の発現リスクを抑える効果があります。
- 【持病のコントロールをする】治療開始前にしっかり管理しておきましょう。
- 【経口投与から経皮剤(テープ、ジェル)に変える】皮膚から吸収させる方法は血栓症などのリスクを低減する可能性があります。
- 【子宮がある場合は必ずプロゲステロンを使用する】子宮体がんのリスクを抑える効果があります。
- 【投与方法を変更する】
閉経前からホルモン補充療法(HRT)を始めるときに確認したいこと

ホルモン補充療法を始める際には、安全に開始できるかを確認しましょう。
医師による診断と検査が必要
更年期障害の診断は簡単ではありません。そのため、まずは医師による診察を受け、更年期症状に似た病気(関節疾患、うつなど)が隠れていないか確認することが重要です。開始前には、血液検査・乳がん検診・子宮がん検診も行います。
閉経前にホルモン補充療法(HRT)が可能かチェック
ホルモン補充療法は誰でも受けられる治療ではなく、行えない人や注意が必要な人がいます。
禁忌(行ってはいけない人)
以下に該当する方は、原則としてHRTは適用されません。
- 重度の肝疾患がある
- 現在または過去に乳がんにかかったことがある
- 現在子宮体がんにかかっている
- 血栓症・脳卒中・心筋梗塞の既往がある
慎重投与(医師と相談しながら使える人)
以下のような方は、医師と十分に相談のうえ、メリットとリスクを評価しながら治療を検討する必要があります。
- 去に子宮体がんや卵巣がんにかかったことがある
- 肥満がある
- 60歳以上で新規にHRTを開始する場合
- コントロール不良の糖尿病や高血圧がある
- 片頭痛がある
上記以外にも注意が必要なケースがあります。持病がある方は、必ず事前に医師と相談し、安全に治療を始められるか確認しましょう。
ホルモン補充療法(HRT)に関するQ&A

ホルモン補充療法に関して、よくある質問にお答えします。
何歳から治療できる?
HRTを始める年齢に一律の決まりはありません。
閉経の5年前から更年期症状は起きることがありますが、実際にいつ閉経するかを正確に予測することは困難です。
一般的には、更年期に入った時点で早めにHRTを開始するほうが、心筋梗塞のリスク低下につながり、重篤な副作用も少なくなるとされています。症状が複数当てはまるようなら、閉経前であっても一度医師に相談し、治療開始の可否を検討しましょう。
何歳まで続けられる?
HRTをいつ終了させるかについて明確な年齢制限はありませんが、これらの条件を満たしていれば、治療を続けることが可能です。
- メリットがデメリットを上回る
- 患者本人が継続を希望している
- リスクについて理解している
医師と相談のうえで、自分の体調や生活に合わせた判断をしていきましょう。
ホルモン補充療法(HRT)の他に治療の選択肢はある?
更年期障害の治療法には、ホルモン補充療法以外にも、カウンセリングや漢方、認知行動療法や生活習慣の改善があります。
これらはHRTと並行して行うことも可能で、組み合わせることでより症状が改善する可能性があります。
閉経前の辛い症状にホルモン補充療法(HRT)は有効な選択肢の一つ
更年期は、誰にでも訪れる人生の節目です。特に閉経前は以前とは異なる生理前後の症状に悩まされがちで、日常生活に支障をきたすこともあります。ホルモン補充療法は、そのような症状を和らげ、生活の質を高める有力な選択肢のひとつです。
ただし、すべての方に同じ方法が適しているわけではなく、効果やリスクは人により様々です。大切なのは、自分の体やライフスタイルに合った方法を医師と一緒に考えることです。
「更年期だから仕方ない」と我慢する必要はありません。閉経前でも、ホルモン補充療法を行うことで快適な毎日を送れる可能性があります。医師と相談しながら、安心して日々を過ごせる方法を探してみましょう。